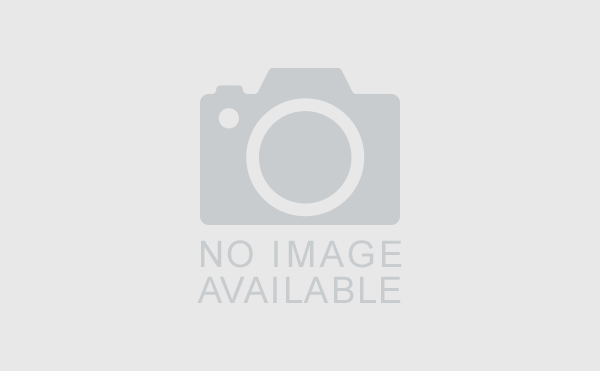遺言を残したほうがいい人とは?
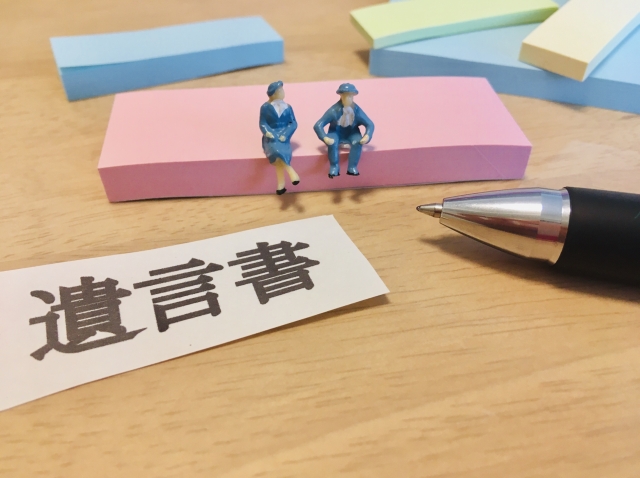
こんにちは、行政書士の奥田です。
遺言を残すことは、誰にとっても意義があり、残しておくことのメリットはたくさんあります。
しかしながら、人生はいろいろですから、すべての人が一律に同じような家族構成であるわけはないし、人間関係も様々です。持っている財産の量や内容も違いますよね。
今回は、その中でも”遺言を残したほうがいい”人について書いていきたいと思います。
これから書いていくパターンに少しでもあてはまるなと思われた方は、ぜひとも遺言を残すことを検討されてみてください。
1.遺言がないことでトラブルになる可能性が高い
(1)夫婦の間に子供がいない
民法に定められている、法定相続人の相続の順番として、(配偶者は必ず相続人となりますが)第1順位は子供です。子供がいない場合は第2順位として被相続人の直系尊属(父母や祖父母…)となり、さらに直系尊属もいない場合は第3順位として被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります(法定相続については、また別の機会に書いてみようと思います。)。
遺言がない場合、相続について法定相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
そうすると、亡くなった方の配偶者は、自分の妻(または夫)の父母もしくは兄弟姉妹とそろって遺産分割協議を行うということになります。
妻(または夫)の預金や自動車、不動産の名義変更をするにも、義理の父母や兄弟姉妹の同意が必要になってくるということです。
普段から連絡を取っていない、等の間柄だったりすると、財産を分け合う話し合いにおいてはトラブルになる可能性も考えられます。
このため、例えば「自分の死後、財産はすべて配偶者に残したい」という思いがあるのであれば、遺言を残しておくことが最善であると考えます。
(2)過去に離婚を経験しており、元配偶者との間にも子供がいる
元配偶者は法定相続人とはなりませんが、元配偶者との間に生まれた子供は、(自分に親権がなく、全然会ってもいない間柄であっても)法定相続人となります。
そうすると、現在の配偶者と、その間に生まれた子供(いる場合)にのみ財産を残したい場合等は、遺言がないと、元配偶者との間の子供とも遺産分割協議が必要になります。”顔も知らない、連絡も取ったことがない”といった間柄で、トラブルに発展してしまうことは想像に難くないと思われますので、遺言を残したほうがよいでしょう。
(3)相続人の仲が悪い、相続人がたくさんいる
家族の仲が悪く、普段から揉め事が多かったり、そもそも連絡も取り合っていないような間柄の家族である場合は、遺産分割協議においては、財産のことですから、ますます揉めてしまう可能性も高くなると思われます(少なくとも、円満に話し合うことはあまり期待できないように思われます。)。
また、相続人がたくさんいる(子供がたくさんいる、もしくは子供や親はおらず、兄弟がたくさんいる)場合も、人数がいればいるだけトラブルになる可能性も上がります。トラブルにならないとしても、みんな集まって協議すること自体が、そもそも大変です。このような場合も、遺言に残したほうがよいでしょう。
(4)障がいを持つ方がいる、認知症の方がいる
相続人の中に、障がいを持っていること、もしくは認知症の症状があることで、判断能力がない方がいらっしゃる場合は、遺言を残したほうがよいでしょう。
遺言がなく、遺産分割協議を行う場合、判断能力がない方は協議に参加することができません。そうすると、その人の代わりに遺産分割協議に参加してくれる「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
成年後見人の選任手続きには1年以上時間がかかることもあり、相続の手続きがなかなか進められない、、という事態になってしまいます。また、専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)が成年後見人に選任された場合は、その費用もかかります。
遺言を残しておけば、遺産分割協議をする必要がないので、スムーズに相続手続きを進めることができ、安心です。
2.財産の残し方について自分の中に明確な意思がある
(1)法定相続人以外に財産を残したい
例えば、「子供のお嫁さんには日頃から本当にお世話になったから」とか「〇〇さん(親しい友人)に残したい」という場合は、遺言に残したほうがよいでしょう。
基本的に、遺言がない場合は、法定相続人全員による遺産分割協議になりますので、残された財産は法定相続人の間で分け合うことになります。
また、仮に事前に相続人の方に希望を伝えていて、それを叶えてくれたとしても、結果的に贈与税がかかってしまい、受け取った人の負担になってしまったりするかもしれません。このため、遺言してしっかり形にしてあげたほうが、受け取る側としてもありがたいのではないでしょうか。
※子供のお嫁さんにお世話になったから、、といったパターンの場合、「特別の寄与」という制度もありますが、これは受け取る側(この例でいうとお嫁さん)のほうから相続人に対して請求する制度であり、相続人との話し合いでまとまらなかったら、家庭裁判所に調停を申し立てる、、という流れになりますので、双方の負担が大きくなってしまいます。やはり、残す側から、遺言として形に残してあげたほうがよいかと思います。
(2)誰に、何をどのくらい残すか指定したい
こちらはトラブル防止の観点でもいえることではありますが、後の遺産分割協議で相続人同士での話し合いで決められるより、自分の希望通りに財産を分けたいという思いがあるなら、遺言に残したほうがよいでしょう。
例えば「長男のほうがよく家に顔を出してくれたし、いろいろと助けてもらったから長男に多く残したい」という場合も遺言で指定することができます。この場合は、自分の死後、その遺言の内容で揉め事にならないように、しっかりと付言事項等で説明を書き残してあげることも必要でしょう。
(3)内縁の妻(夫)に残したい
内縁関係の妻や夫は、法定相続人にはなりません。事実婚のご夫妻も多くおられる昨今ですが、どちらかが亡くなったときに相続権はないため、財産を残したい場合は遺言として残しておく必要があるので注意が必要です。
(4)寄付したい
自分の財産を世の中のために役立てたい、〇〇の施設に寄付したい、という思いがある方は、遺言に残しましょう。
3.その他
(1)相続人がいない
法定相続人がいない場合、その方の財産は最終的に国庫に帰属(国が取得)します(民法第959条)。
それを望まない場合(親族や友人等の特定の誰かに分けたい、寄付をしたい)は遺言を残したほうがよいでしょう。
(2)相続人はいるけど行方がわからない
「法定相続人は確認できたけれども、連絡がつかない」「数年前から行方がわかっていない相続人がいる」場合は、遺言を残したほうがよいでしょう。
遺言がないと、”相続人全員での”遺産分割協議が必要になります。上記の場合、遺産分割協議が成り立たず、いつまでたっても相続財産の分配ができない状況になってしまいます。
また、最終的には家庭裁判所の手続として「不在者財産管理人」の選任申し立てや、「失踪宣告」の申し立てという方法もありますが、これは相続人にとってかなりの負担になってしまいます。
遺言があれば、これらの負担をかけずに済みます。
(3)事業をしている
事業をされている人、農業を営んでいる人も、引き継ぎを円滑に進めるために、遺言を残したほうがよいでしょう。
事業継続に必要な財産、設備、土地等を、事業の後継者に遺言でしっかりと引き継いであげましょう。
(4)不動産を所有している
不動産を所有している場合も、相続人が複数いる場合は、遺言でしっかり指定したほうがよいでしょう。
まず、その不動産(家)に住み続ける人にとっては死活問題になりますし、相続人で共有するということもできますが、そうなると、維持管理について(特にお金)揉めたり、売却を考えたときに全員の同意が必要になったり、トラブルの心配がつきません。
4.最後に
今回は、遺言を残したほうがいい人、について書きました。
「結構当てはまるかも…」という方は多いのではないでしょうか。
しかしながら「うちは家族みんな仲良いし、大丈夫!」と、残す側も、残される側も今は思っている方も多いと思います。
また、「まだ若いし、考えるのはもっと後でいいや」という方も多くおられると思います。
しかし、人生いつ何が起こるかわかりません(悲しいことは少ないに越したことはありませんが…)し、財産のことですから、絶対に円満にいくとは限らないのは、人間ですから仕方のないことです。
遺言として形に残すことで、残された家族達に負担をかけずに財産を分ける準備ができれば、残す側も残される側も、安心なのではないでしょうか。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。